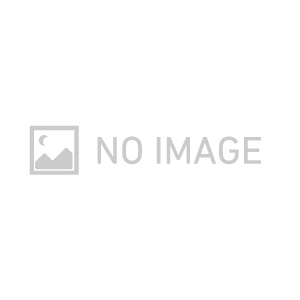ブロックチェーン・インパクト vol.2
ブロックチェーンのどこが「スゴイ」のか?

インターネット以来の産業革命と呼ばれる「ブロックチェーン技術」。経済・社会へのインパクトは計り知れないといわれるが、それはなぜか?
連載第2回は今までの経済社会のシステムと比較して、どのようなことが可能になっていくのか、について見てみる。
なぜブロックチェーンは革命なのか?
今までのパラダイム
「ブロックチェーン」は暗号技術によってデータ化された帳簿である。もっとも、今まででも情報はデータ化されてデータのやり取りは盛んにおこなわれていたし、データはサーバーに保存されて管理されていた。
しかし、今までのパラダイムでは、情報を管理する主体が存在し、情報はまとめて中央に集められて管理されるのが一般的な考えだった。
例えば、フェイスブックには世界中のユーザーがコメントや写真データなどを投稿するが、それはフェイスブックが管理しているものだ。また、今までもマイレージやポイントなどの決済手段たりうるものはあったが、これも、航空会社やポイントを発行する企業が管理している。
したがってユーザーは中央で管理する大企業にアクセスして何らかの利便性を得るが、それはサービス提供者と多くのユーザー、という中央集権の構図であった。
しかし、この一点集中型の方式では、常にサイバーアタックの危険性や、情報操作の危険性がある。
そこで、コンピュータを分散化させて、複数のコンピュータがデータを管理してネットワークを運営する、という発想が生まれた。これは、コンピュータ業界では珍しくないもので、従来においても、リスク分散のために管理者・管理場所を複数個所に分散させようという発想はあった。
しかし、この方式は容易に受け入れられるものではなかった。中央で管理する者がいない、分散型のネットワークには常に付きまとう大きな問題がある。
二重払いのリスク
AさんからBさんへ価値が移転するときには、Aさんが別のCさんにも価値を移転していないか、という問題は古くからある根本的な問題である。
不動産でも二重譲渡をしていないか、ホテルではダブルブッキングされていないか、という問題であるが、これは誰かが管理しているということを信頼して私たちはサービスの提供を受けている。
本当にAさんが支払ったのか?
コンピュータが分散化されていると、送信されてきた情報が真実の情報なのか、ということを判定する手段が必要となる(「ビザンチン将軍問題」といわれる)。
つまり、攻撃者が多くのノードから間違った情報を発信させることにより、真実でない情報がはびこる結果を回避しなければならない。

ブロックチェーン技術が解決した!
サトシ・ナカモトの論文をきっかけとしたブロックチェーン技術の発展は、上記の問題を見事に解決している。
ブロックチェーン技術の上で、二重に支払(価値の移転)をするためには、前の取引を改ざんして新たな取引を書き込む必要がある。
しかし、一部の取引を改ざんするためには、その後の取引についても改めて暗号化する多大な労力が必要となるために、二重払いのリスクは極めて低くなっている。
また、情報が真実かどうか、という問題は、攻撃者一味が全体の3分の1未満である場合には誤った情報が真実と認定されることを防止することができる、ということが著名な数学者によって証明された。
ブロックチェーンネットワークの中で、3分の1以上の支配力を持つことは経済的にもほぼ不可能であり、仮にそのような力を持てば、そのブロックチェーンネットワークへの信頼は薄れ、利用者は減り、仮想通貨の価値は下落する。つまり、そのような力をもつメリットがない。
さらに、多くのブロックチェーンシステムでは、価値を受け取った側は、本当にAさんから送信されたものか、を確認するために暗号を解読する「秘密鍵」を取引データの記録と同時に受け取るシステムとなっている。この秘密鍵によって実際に暗号が解読できれば、確かにAさんから送信されたものであると確認できる。
ブロックチェーンの大きなパラダイム転換
ブロックチェーン技術は、取引の記録が改ざんされたり、誤った情報が記録されたりするリスクが極めて小さくなっている。
ネットワーク自体が、ある決まったルールによって自律的に取引データの記録(帳簿への書き込みと表現してもいいだろう)を蓄積していくため、そこに中央管理者は必要ない。
実際、ビットコインについても、開発者はいるものの、ビットコインを発行している主体というのはなく、あらかじめ定められたルール(プロトコル)によってビットコインの発行、送金、受取、保管がなされているだけだ。
このようなことが可能となったのは、信頼の相手が「中央管理者」ではなくて、「ブロックチェーン技術を活用したシステム」自体になったからであるといえる。
今までは、信頼の相手は、「円」であれば「日本銀行」や「メガバンク」、不動産取引であれば「法務局」、SNSであれば「フェイスブックなどのSNSを管理している会社」という中央で管理している主体であった。

しかし、ある一定のルールに従って記録する、という作業はコンピュータの最も得意とするところであり、これによって取引はどんどん自動化・簡素化されていく。
ブロックチェーンがインターネット以来の産業革命であるといわれているのは、管理主体がない自律的なネットワークを利用することによって、中央管理者を介さない価値の移転が自由にできる基盤が整ったから、であるといえるだろう。
ブロックチェーンの先駆者・ビットコイン
これまで「ブロックチェーン」という技術についてその特徴や今までのシステムとの違いについて考えたが、ブロックチェーンとは技術の総称であって、「取引データのブロックを」「チェーンのようにつなげて」「分散されたコンピュータで管理する」方法については世界中で改善が試みられている。
次回は、その先駆者ともいえる「ビットコイン」について、その仕組みをできるだけわかりやすく説明してみよう。