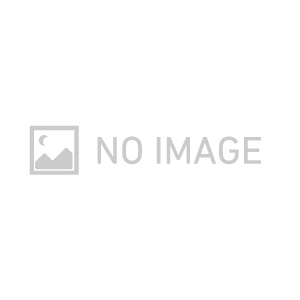ブロックチェーン・インパクト vol.5
イーサリアムとリップル

「価値のインターネット(Internet of Value)」。
リップル(Ripple)の共同創業者でありExecutive Chairmanのクリス・ラーセン氏は自社の目指すべきサービスをこのように表現する。
インターネットの発明・普及によって情報は瞬時に世界中を飛び回わるようになり、情報の質についても、文字、画像、音楽、映像と飛躍的に上がっていった。
しかし、お金をはじめとする価値の移転については、いまだ数日を要する場合があるし、少額の移転については手数料が高すぎて制限されるなど、まだまだ発展途上だ。リップルは、インターネットの次の段階を見据えている。
世界で流通している仮想通貨の種類は約1500種以上であるといわれているが、その中でも取引量が多いのはビットコイン、イーサリアム、リップルである。今回はイーサリアムとリップルの有用性について取り上げ、ブロックチェーンが今後どのような分野に利用されていくかの足掛かりを見つけたい。
INDEX
イーサリアム(ethereum)
決済だけではない!
ビットコインは今や投機の対象としか見られていない感をぬぐえないが、当初は、ビットコインは中央集権化された権力から独立した決済手段を確立する目的で開発されたものである。
しかしブロックチェーン技術は決済のみに応用されるものではない。そこで、決済のほかにもいろいろな分野に応用できるブロックチェーン技術のプラットホームができないか、という発想から考案されたのが、イーサリアムである。
イーサリアムはロシア共和国モスクワ出身の当時弱冠19歳、ヴィタリック・ブリテンによって生み出された。当時は、アプリケーションの設計ごとにブロックチェーンを開発していたが、彼は、それでは非効率的だと感じた。
彼は、あらゆるサービスが、少しのコードを書くだけで、一つのオープンソースのプラットホーム上でブロックチェーンを使ったサービスを提供できないかと考えたのだ。
最大の特徴であるスマートコントラクト
イーサリアムの最大の特徴といえば「スマートコントラクト」を実現させる機能を実装している点である。
「スマートコントラクト」とは、契約、決済を自動化しようとする考え方で、ある一定の条件がそろえば、契約の実行と仮想通貨(イーサリアムの場合は仮想通貨「イーサ(ether)」)での決済を自動的に行うシステムを指す。
「スマートコントラクト」の概念はよく自動販売機に例えられる。これは、スマートコントラクトの概念を考案したといわれるNick Szabo氏の説明に端を発したものである。
すなわち、自動販売機は、コインを持っている利用者ならば誰でもボタンを押すことで缶ジュースを手に入れることができ、ここでの決済、契約はほぼ自動的に行われる。この一連の手続きが自動的にブロックチェーン上に記録されることによって一連の手続きが今まで以上にスムーズに行われる。
ブロックチェーン上でこれらの手続きがすべて終了することになれば、今までに中間に必要だった、仲介機能や書類の照合作業、請求書の発行や代金の振り込みなど、一連の手続きは不要になり、多くの手間と手数料、人件費の削減になる。
この応用分野は幅広く、スマートキー(鍵)と組み合わせることで、スマホのアプリでホテルのカギを開けるとともに決済まで終了している、ということや、自動車、自転車、民泊などのシェアリングサービスについてもすべてスマホのアプリで手続きが完結するということが実現する。

(シェアリングサービスのほか、対面の必要のないサービスには爆発的に普及する可能性がある。)
このイーサリアムの有用性には世界中の多くの大企業が目を向けている。「イーサリアム企業連合(EEA)」には、マイクロソフト、JPモルガン、三菱UFJグループ、ファイザー、昭和シェル石油など多くの大企業が参加し、イーサリアムプラットホームを活用したサービスの実現に向けて、実証実験を行っている。
リップル(ripple)
国際間の価値の移動に着目
ブロックチェーンは多種多様な分野に応用可能であるが、どの分野に応用するかで、いろいろな姿にとって代わる。リップルは、銀行間の資金移動、特に国際間の資金移動に着目したサービスである。すでにリップルはイングランド銀行との実証実験において即時の国際間送金の検証を行っており、その実現に向けて大きな一歩を踏み出している(2017年7月)。
今までの銀行間送金システム
現在の銀行間の送金は、中央銀行を介して行われている。つまり、国内の各銀行は中央銀行(日銀)に口座を持っており、各銀行間で口座の残高を増減させることにより、銀行間の資金移動を行っている。
国際間の資金移動となるとさらに複雑で、国際銀行間通信協会(SWIFT)を介して情報がやり取りされ、送金手続きが行われている。
現在では、国内の送金システムでは数日以上かかるケースはほとんどないが、金融機関によっては数時間かかるケースもあり、手数料も高額だ。
国際間での資金移動については、いまだに問題が多く、特に流動性の低いマイナーな通貨では資金移動に3~5日かかるケースもある。また、手数料も高額で、マイナー通貨の少額の資金移動はハードルが高い状況だ。
リップルの目指す資金移動システム
リップルは、独自の暗号技術と特殊な帳簿技術(「XRPレジャー」と呼ばれる、一般のブロックチェーンとは異なる技術)によって、各国の通貨をブリッジすることで、時間と手続き、手数料を減らすことを目指している。
現在、特にマイナー通貨の国際間送金では、いくつかの取り扱い国際銀行を経由して、またいくつかの通貨を経由して送金されている。リップルの方法では、この中間通貨を「XRP(エックスアールピー・リップルの仮想通貨)」一つにして、XRPを仲立ちにして国際間送金を行おうとするものである。

(マイナー通貨ではハイパーインフレの危険も。)
投機の対象だけではない!実用的なトークン
上記で紹介した仮想通貨のほかにも日本で売り買いできる仮想通貨はいくつかある。しかし、イーサリアムとリップルの例を見ると、仮想通貨は単なる投機の対象ではなく、実経済社会において大きなインパクトを与えるトークンであるということの一端を垣間見たのではないだろうか。
次回は、応用編の始まりとして、各メディアで取り上げられているICO(イニシャル・コイン・オファリング)について取り上げる。ICOとは何なのかを深堀してみよう。