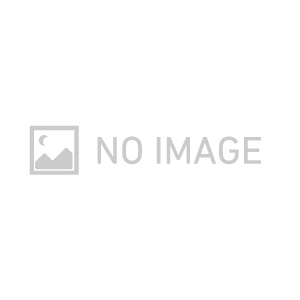非上場株式の取引が可能となる株主コミュニティ

「株主コミュニティ」という制度は企業側にも投資家にもメリットがあると言われています。「株主コミュニティ」の仕組みや投資家にとってのメリット、注意したいリスクを詳しく解説しますので、投資をお考えの方はぜひ参考にしてください。
INDEX
株主コミュニティとは、企業や投資家をサポートする制度
株主コミュニティは非上場株式の流通取引や資金調達をサポートする制度で、2015年の5月に創設されました。
もともと、株主コミュニティは制度としてはあったものの、どの証券会社からも申請はありませんでした。しかし、最近になり、ようやく申請する証券会社が少しずつ現れ、数年前では考えられないような大きな変化が見られています。
証券会社が取り扱う未公開株制度としては、これまでグリーンシート制度がありましたが、発行会社への適時開示義務による取引銘柄数の減少に伴い2018年3月に終了しました。
株主コミュニティが実現したら?
これまで、地元のバス・鉄道会社の株主優待券を手に入れたい方や相続した非上場株式を売却したい方のほかにも、企業側の事業承継や資金調達においても非上場であることが取引のネックになっていました。
「株主コミュニティ」制度をクリアすることで、取引する場の確保や幅広いニーズに応えられるようになります。とはいえ、未だにハードルの高い制度であることに変わりはありません。
株主コミュニティの組成と参加方法
企業の場合
株主コミュニティ銘柄として取り扱いたい株式と企業の財務状況を証券会社によって審査され、認められた場合に「株式コミュニティ」が組成されます。
投資家の場合
株主コミュニティを組成する証券会社にて参加申し込みを行います。
※上記は一例であり、詳細は各証券会社に確認しましょう。
株主コミュニティ銘柄は、参加者間もしくは参加者と運営資格を持つ証券会社との間でのみ取引可能となります。
企業や投資家にとってのメリット
投資家が株主コミュニティに参加することで、未公開株式の取引が可能になるほか、株主優待といった企業が提供するサービスを受けられることも大きな利点です。
企業が株主コミュニティを組成することで、自社株を取引する場ができて資金調達しやすくなります。ほかにも地域に根差した株主優待制度で、地元利用者にアピールできます。
投資家が注意したいリスク
株主コミュニティに参加するにあたって投資家が留意したいポイントがいくつかあります。
1、株主コミュニティ銘柄は参考となる取引価格がないことが多く、短期間に価格が大幅に変動することがあります。
2、投資先の企業が倒産した場合など周辺の状況によって大幅に価値が失われる可能性があります。(投資した金額が0になることもあります。)
3、有価証券報告書を公表していない企業もあります。
4、取引は証券会社の店頭でのみ行われます。
5、上場銘柄と違い流動性が低く、好きなときに売却や購入ができるわけではありません。
日本証券業協会の自主規制や非上場株式投資へのネガティブイメージから、これまで眠った制度と言われていた株主コミュニティ制度ですが、周囲は徐々に変化し始めています。
最近では株式型のクラウドファンディングと株主コミュニティを絡めたサービスが実現する動きがあります。
実現すれば、投資家がクラウドファンディングで取得した非上場株式を株主コミュニティ内で売買できるようになり、これまで問題視されていた非上場株式の流動性が向上することを期待できます。
気軽に始められる制度ではないため、上記のリスクを踏まえた上でコミュニティへの参加を考えるようにしましょう。